- 16.03.09
『有職故実の話』
(1) ひなまつり考
ひなまつりは、古くから「上巳(じょうし)の節句」と呼ばれているもので、「桃の節句」という名でも親しまれています。
日本の宮廷では、平安の昔から、季節の節目に饗宴を伴う催事を執り行う習慣がありましたが、その「節会(せちえ)」を行う日を「節句」あるいは「節供」と言いました(折口信夫は「節供」が正しいとする)。
徳川幕府は、あまたある節句から五つを選び、「五節句」としました。すなわち、(1)人日=1月7日(七草の節句)(2)上巳=3月3日(桃の節句)(3)端午=5月5日(菖蒲の節句)(4)七夕=7月7日(たなばたの節句)(5)重陽=9月9日(菊の節句)
現代でもなじみ深い行事ばかりですが、中でも3月3日の上巳、いわゆる桃の節句は女子の祝いとして広く親しまれています。上巳という言葉には次のような意味があります。子、丑、寅・・の十二支は、今では年の名前と思われていますが、本来は月にも日にもつけられているもので、一ヶ月のうちに、同じ支の日は二回ないし三回巡ってくることになります。上巳、つまり月の一番初めの巳(み)の日を上巳(じょうし)というのです。
ひなまつりの起源には概ね二説あるとされます。
一つは、「形代(かたしろ)」という紙などで作った小さな人形を川や海に流す儀式で、身の汚れを人形に託して川や海に流すというもの。源氏物語「須磨の巻」の一場面を、与謝野晶子訳本で見てみます。
—今年は三月の一日に巳(み)の日があった。「今日です、お試みなさいませ。不幸な目にあっている者が御禊(みそぎ)をすれば必ず効果があるといわれる日でございます」賢がって言う者があるので、海の近くへまた一度行ってみたいと思ってもいた源氏は家を出た。ほんの幕のような物を引きまわして仮の御禊場(みそぎば)を作り、旅の陰陽師(おんみょうじ)を雇って源氏は禊い(はらい)をさせた。船にやや大きい禊いの人形を乗せて流すのを見ても、源氏はこれに似た自身のみじめさを思った。
もう一つ、単純な人形遊びとしてのルーツもあります。同じく源氏「紅葉賀の巻」。
—源氏の春の新装を女房たちは縁に近く出て見送っていた。紫の君も同じように見に立ってから、雛人形の中の源氏の君をきれいに装束させて真似(まね)の三代をさせたりしているのであった。
禊ぎと遊びという異なる二つの儀式が、時代の流れの中で混交し、洗練と集約を重ねながら現代に至ったのです。(S)
(2) 袴について
卒業式シーズンを迎え、町中に袴姿の女学生が目につくようになりました。袴は上古から現代まで、大変長きにわたって親しまれている服飾です。
明治政府が刊行した、我国最大の官選百科事典として知られる「古事類苑(こじるいえん)」には、袴についての説明が多く書かれています。現代語訳で引用してみます。まず、男子袴について(服飾部十四)。
「はかまという呼び方は既に神代の時代に見られる。袴には表袴、大口袴、小口袴、指貫、長袴、半袴などの種類がある。表袴は『うえのはかま』といい束帯の時に用いるもの。大口袴は表袴の下に重ねて着用するもので、生絹、平絹、精好などで作り、多くは赤地。小口袴は大口袴に対するよびかたで、裾口が小さなものをいう。指貫(さしぬき)は緒紐で裾口をくくるもので、直衣(のうし)の時に着用することが多い。長袴は、裾を長く引いた、武家が用いたものである。裾を引かないものを半袴というが、そのうち、襠(まち)を高くして、裾をやや広く作ったものを馬乗り袴といい、今日、広く用いられている袴のことである」
現代の男子袴といえば、その馬乗り袴と、襠がない行灯(あんどん)袴に大別されますが、上記の説明文に行灯の名前はなく、明治、大正の頃までは、行灯袴はあくまで略装であったことがうかがわれます。現代では、女子袴など、行灯も礼装として用いられています。
女子袴についても「古事類苑」から引用してみます。
「婦人の袴には、表袴、下袴、重袴等の数種あり、単袴、張袴、打袴などはその製法をもって名とする」。
この張袴、打袴について、江戸時代の有職故実研究家である伊勢貞丈(1718〜1784)は「板引きにして張ったものをはり袴といい、やはらかにしたものを打袴という」とあります(貞丈雑記)。
また貞丈は、女子袴の変遷についても次のように記しています。(安斎随筆)
「袴は足を覆い隠すためのものであり、古くは武家の女どもも紅袴をはいた。しかし、室町殿の代(室町時代)からは常には着ず、晴れの時のみ着るようになった。ただし、応仁の乱以降のことである。今は将軍家の御台所のほかは着る事がない」
伊勢貞丈の時代は享保年間(将軍吉宗の治世)ですが、少なくとも、その頃までは、一般的には武家の女性は袴を用いなかったことがうかがわれます。
袴の構造は単純ですが、機能的にも装飾的にも優れているのは、ヒダと襠(まち)があるところです。両者の存在によって、所作にかなり融通性が与えられます。
ちなみに、能楽や日舞では襠を低く仕立てた「仕舞袴」を用いることがあります。日舞の男踊りのように、腰を落とし動きの激しいものを踊る場合は、普通の馬乗り袴では所作に不都合が出るためです。 (S)
(3)彼岸
今年の春分の日は3月20日でした。別名、彼岸の中日ともいわれます。春分は二十四節気の一つで、昼と夜の長さがほぼ等しくなる日のことです。天文学的には、太陽が春分点を通過して太陽黄経が0度となる日のことで、この春分と、前後3日を合わせた7日間が彼岸です。彼岸が春と秋にあるのは御存知のとおりです。
彼岸は、もともと仏教の言葉で「煩悩の苦を脱して菩提の果を得る」という解脱の域に達することをいいます。それに対して煩悩から脱することができずにさまよっていることを「此岸(しがん)」といいますが、つまり現世のことです。
彼岸の7日間を彼岸会といい、古来、仏事を執り行い先祖に供養してきたものです。この7日間にそういうことをする理由については諸説ありますが、一般的にいわれているのは、春分・秋分には太陽が真西に沈むので、弥陀の国といわれる西方浄土に導いてくれるというものです。
我国で彼岸会が行われた最も古い記録として、延暦25年(806年)というものがあります。桓武天皇が崩御した際に、亡き皇子の早良親王の鎮魂のために、全国の国分寺の僧が読経したのが始まりだとされています(古事類苑歳時部)。
二十四節気、五節句といった暦日の他に、季節の移り変わりを知るために設けられた「雑節」というものがあります。彼岸もその一つで、他には節分、社日、八十八夜、入梅、半夏生、土用、二百十日、二百二十日があります。
このうち社日というのは、現代では馴染みの薄い言葉ですが、春分、秋分に一番近い戊(つちのえ)の日のことをいいます。春分に近い日を春社(しゅんしゃ)といい、今年は3月17日です。今年はたまたま社日と彼岸の入りが重なりました。
十干の一つ戊(つちのえ)はその名の通り土にちなんだもので、社日は農家の種蒔きの目安日として用いられました。彼岸も社日も古暦で用いられた言葉ですが、暦がもっとも活用されたのは農業で、農業主体の社会では、季節の変わり目がいつなのかということが、きわめて重要なことがらでした。
春秋に農作物の順調な生育と収穫を先祖に祈っていたものが、中世に至って仏教思想と混じり合い、彼岸参りという現在も続く行事になったと考えられます。これが宮中では歴代の天皇・皇后の霊を祭る皇霊祭となり、戦後、春分・秋分の日と改称されて現在の国民の祝日につながっています。(S)
* 参考:新しき年中行事(小林鶯里 1924)、宮中三殿並に祝祭日解説(皇典講究所 1912)
(写真) 彼岸は作付けの目安
(4)源氏物語・桐壺
源氏物語は、世界最古の長編小説といわれますが、きわめて長大で、非常にすぐれた王朝文学です。そして「桐壺」は、五十四帖にもわたる壮大な物語のプロローグであり、紫式部の小説家としての秀逸さが、本帖の冒頭にすでに現れています。
帝の寵愛を一身に受けた一人の妃がいました。あまりの寵愛ぶりに他の女御、更衣から嫉妬され、さまざまな意地悪を受けることになりますが、この薄幸の女性こそ、物語の主人公である光の君(光源氏)の母、桐壺の更衣です。しかし、物語では、なかなかこの女性が何者かが明かされません。源氏が誕生し、帝の寵愛がいよいよ深く、人々の妬みもますます募る中、女性の苦悩が最高潮に達したところで、唐突に「御局は桐壺なり」という言葉が投げ出され、桐壺という場所、そこに住む彼女の身分や心情が一気にあきらかにされるのです。
源氏物語が、世界中の人々から賞賛される理由の一つが、このような淡々とした描写の中にひそむ劇的効果であることはまちがいありません。
「御局は桐壺なり」に続いて、源氏物語・桐壺の帖には次のように書かれています。
「あまたの御方々を過ぎさせ給ひつつ、ひまなき御前渡りに、人の御心を尽くし給ふも、げにことわりと見えたり」(この桐壺の部屋は、御座所の清涼殿からはかなり離れていて、陛下は、多くの女官たちの部屋の前をひっきりなしに渡らせられるので、そのたびに『またか』と女官達が気をもむのも、無理のないことだ)。
桐壺の壷とは庭のこと。桐壺は、桐の木が植えられた庭がある部屋という意味です。この部屋は御所の東北、陰陽五行でいうところの丑寅、つまり鬼門の方向にあります。そういう場所に住む女官が、どのような立場の者であり、そういう立場の女性が帝の寵愛を独り占めするとどういうことが起きるのか、「桐壺」という名前一つで読者は今後の波乱の展開を予想できるのです。紫式部の、作家としての尋常ではない技量を、ここにも見ることができるのです。(S)
*参考:島津久基「釋評源氏物語巻1」
桜前線が北上しています。
現代では、花といえば桜のことを指すのが普通ですが、平安時代以前は、花といえば梅であった・・・ということがしばしば言われます。その根拠として万葉集に登場する桜と梅の歌の数が示されます。すなわち、万葉集で梅を題材にした歌は118首もあるのに対し、桜の歌は44首のみであるということです。
一方で、そんなことはない、花といえば昔から桜と決まっていたとする説もあります。コノハナサクヤヒメ(木花開耶姫)は、古事記、日本書紀などの日本神話に登場する美しい女神ですが、コノハナとは何の花かということについて、神代記(8世紀、天平年間成立)には次のように記されています。
「木ノ花開耶姫ありて、伊勢朝熊の神社に桜樹をその霊とせしこと、古記にも見えて、桜ノ宮とも称せり」
万葉集の時代、いまだ国風文化が確立せず、なにごとも中国風を取り入れることが知識人の習いでした。中国では桜がポピュラーでなかったことも、桜より梅となった一因なのかもしれません。
〈歌川国貞画 六条御所花之夕宴 1855〉
—春高楼の花の宴。
土井晩翠作詞、滝廉太郎作曲による「荒城の月」は、平安以来の今様と西洋音楽が融合した、明治の奇跡ともいえる名曲ですが、ここで歌われる花の宴とは、花見のことです。
「如月の二日あまり、南殿の桜の宴せさせたまふ」の書き出しで始まる源氏物語第8帖・花の宴は、まさに紫宸殿での花見の場面。宮中での花見の習慣は、光源氏の時代からさかのぼること200年、弘仁三年(812年)に始まったといわれています。日本後記によれば、この年、帝の庭園である神泉苑で、嵯峨天皇が「花宴の節」を開いたのが花見のルーツといわれています。
その嵯峨天皇が詠んだ漢詩に「神泉苑花宴賦落花篇」というものがあります。
「過半青春何処催 和風数重百花開」で始まる七言二十四句の長編詩で、桜花の一瞬の輝きを愛惜しています。
嵯峨天皇はことのほか桜を好まれたようで、他の貴族たちも競うように桜を愛でて、これが現代日本人の桜好き、花見好きにつながったのではないでしょうか。(S)
4月5日(火)、衣紋道高倉流東京道場で、恒例の勉強会「雑事抄を中心に宮廷装束を見る」(主催/有職文化研究所)が開かれました。伝説的な有職書として知られている「雑事抄」を基に、平安時代から連綿と続く装束や物の具について、衣紋道高倉流の仙石宗久宗会頭が、詳細に、わかりやすく解説するものです。
今回は、夏物束帯の衣紋実演を中心に、平安、室町期に用いられた「磯高の冠」や束帯、太刀など、貴重な物の具についても説明されました。
雑事抄というのは、室町時代前期の南北朝時代(15世紀前半)に有職家として活躍した高倉永行の著わした文書のことです「
永行の父・永季は高倉家の祖で、高倉家は有職故実を家職として朝廷に仕えた公家です。このような特殊技能を有する家を「半家」とよび、他には、和歌・俳句の富小路家、陰陽道の土御門家などがあります。
高倉永行は足利将軍家への衣紋道指導や、朝廷における有職故実の体系化などに尽力し、雑事抄の他、法体装束抄などの著書を残しています。
有職故実(ゆうそくこじつ ゆうそここじつ)の有職とは「先例の知識」のことで、故実は「規範や根拠」のことをいいます。先人の有職故実研究の故に、我国の古文献は質量ともに充実し、日本史学の発展に大きく貢献してきました。 有職故実の範囲は多岐にわたりますが、一般には 1、官職 2、宮殿家屋 3、調度装飾 4、服装 5、儀式作法の5つに分類されます。
雑事抄はこのうちの服装(装束、物の具)についての有職書で、室町時代前期以前の装束文化を正確に知ることができます。今回の講座では、たとえば磯高の冠といえば平安、鎌倉期のスタイルであること。あるいは、束帯に用いる石帯は、鎌倉時代に現代のように前後にパーツが分かれたという説があるが、雑事抄の中には、室町期にも、二部式だけではなく、本来のバックル型のものも存在したという記述がある、といったような、有職故実だからこそ知りうる貴重な話題も、仙石宗会頭から紹介されました。(S)
(参考:出雲路通次郎著 有職故実)
(7)物ノ具のこと
有職故実の範囲は多岐に渡りますが、大きく分けて(1)官職(2)宮殿家屋(3)調度装飾(4)服装(5)儀式作法 に分けられるということを以前に書きました。このうちの服装の中には当然装束が含まれますが、そこに付随する「物ノ具」についても忘れるわけにはいきません。すなわち、冠、沓、太刀、平緒といった物のことです。
物ノ具という言葉の語源について、有職故実辞典(加藤貞次郎編)には、「調度、具足、道具などに同じ。転じて鎧(よろい)の意に用ふ」と書かれています。また、江戸中期の国語辞典「和訓栞」には、「物のふの武具」という意味だともあります。つまり、もともと調度や小物全般を表していたのが、時代がくだるにつれて、主に武具に用いられるようになったということです。
語意の変遷はさておき、装束に物ノ具はつきもので、その装束になぜその物ノ具が必要なのかということは、有職故実の要諦の一つといってもよいでしょう。
*国際文化学園、衣紋道高倉流東京道場では、5月31日より、「物ノ具講座」を開講します。2ヶ月おきの開講で、全6回。1回目はかぶり物(冠、烏帽子、髪上具)がテーマで、直衣布袴の着装を見ながら、衣紋道高倉流仙石宗久宗会頭が解説します。会場は、国際文化理容美容専門学校1号館図書室です。お問い合わせ、お申し込みは下記まで。
TEL03−5459−0075 FAX03−5459−0076
(8)お香のはなし
東京道場では、5月10日(火)、お香の会「名香合わせ」が行われました。衣紋道高倉流の仙石宗久宗会頭の解説のもと、名香「楊貴妃」を聞き比べて楽しみました。
お香には「五味六国」という言葉があります。五味とは辛、甘、酸、鹹、苦のことで、香木の複雑さ、奥深さを表しています。仙石宗会頭は次のような表現で解説されました。
「良い香りがするからといって名香とはいえない。特に一本調子の香りは良くない。甘さ、苦さ、酸味などが複雑にからみあい、表面的に感じられるものだけではなく、目に見えないところのかすかなものを感じ取ることが、日本的な奥の深さである」
ちなみに、六国とは香木の産地、品質などによる分類で、伽羅、羅国、真那伽、真南蛮、佐曽羅、寸聞多羅の6つです。
お香の歴史は古く、推古天皇の時代にまでさかのぼります。聖徳太子伝暦には、推古帝3年(719年)、沈水という香木が淡路島に漂着したのが始まりとあります。爾来、貴族社会では香りを装束にたきしめたりする習慣が広まりましたが、聞香、組香といった、いわゆる香道が確立するのは、室町時代まで待たねばなりません。
伽羅、栴檀、蘭奢待といった自然の香木を焚いてその薫合を賞するのが聞香ですが、その始まりは南北朝時代の佐々木道誉とされています。婆娑羅(ばさら)大名として知られている道誉は時代を代表する風流人でもありました。
その後、室町時代に至り、当て物(賭け事)としての側面が発達し、囲碁や双六などのように、武家の遊びとして発達しました。
その時代、来るべき戦乱を目前にして、つかの間の平和な時間が流れていましたが、江戸時代以降の平安とは異なり、仙石宗会頭の言葉を借りれば「刹那的な」平和でありました。そのため、「遊び」とはいえ、そこには常に戦場に在るような緊張感が漂っていたに違いありません。
香りを嗅ぐことを「聞く」といいます。戦いの中に生きる武士たちは、他の豪族や大名の動静はもちろん、身内の動きにも常に神経を尖らせていたでしょう。雑念を消し、かすかな香りを「聞く」ことは、単なる遊びの域を超えて、重要な精神修養でもありました。
余談ですが、香席では、菓子や煙草の類は禁じられ、唯一許されたのは淡味の漬け物でした。そのため、現代に至るまで、漬け物のことを「香の物」といいます。
東京の美容専門学校は国際文化理容美容専門学校。美容師・理容師の国家資格免許の取得に向けてヘアメイク・カット・ネイル・ブライダル・エステ・着付など、美容のすべてを学ぶ環境です。技術専門の教員が中心に授業や就職面をサポートします。また入学者を募集しています。総合型選抜(旧:AO入学)、学校推薦型選抜【指定校制】(旧:指定校推薦入学)、学校推薦型選抜【公募制】(旧:公募制推薦入学)、一般選抜(旧:一般入学)などのご相談は、オープンキャンパス・個別の見学会にてお待ちしております。
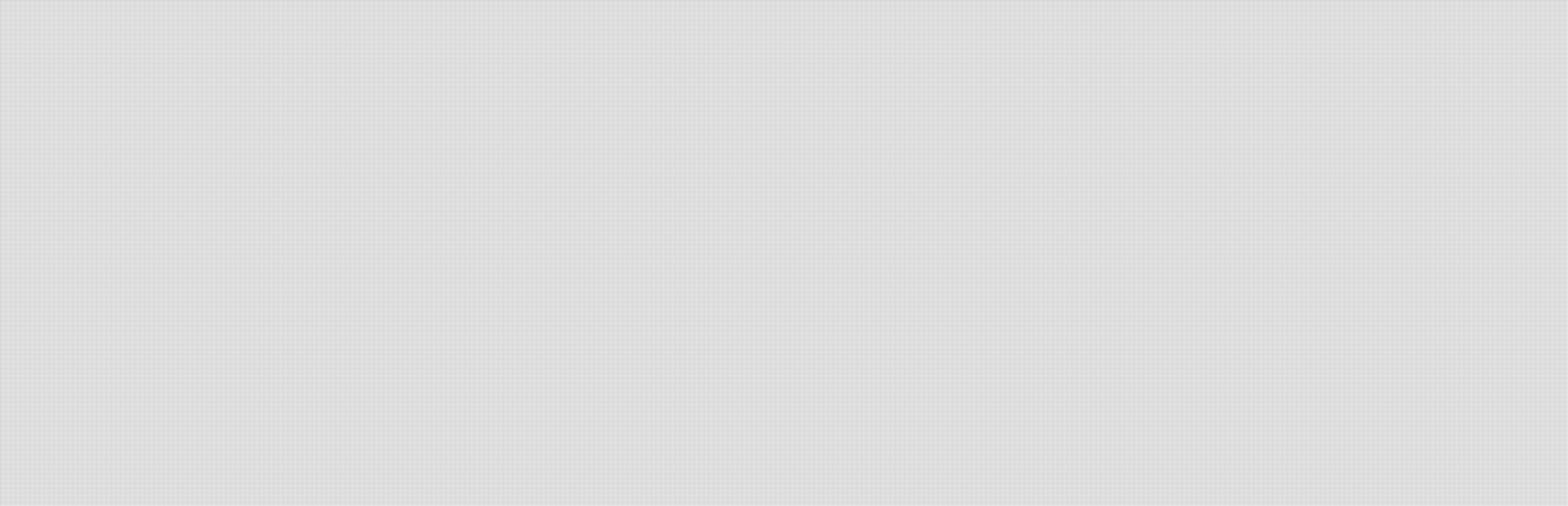













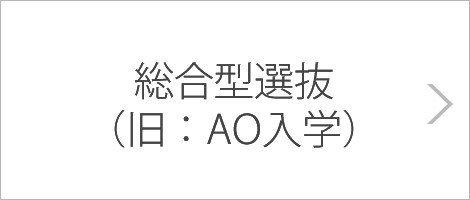



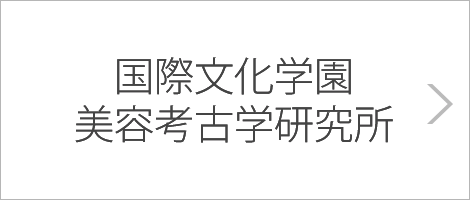

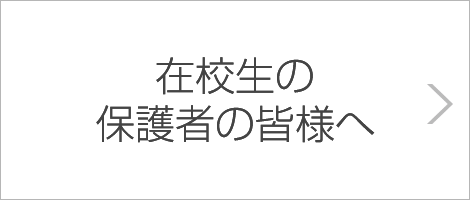


 ページ上部へ
ページ上部へ