- 25.03.31
江戸の美意識に習う
今日で3月も終わるが、3月といえば真っ先に思い浮かぶのが[雛まつり]。
今も[流し雛]といって[災い]を[人形]に移して川に流すといった風習が残る地域もあるとおり、[雛まつり]はもともと[人形](ひとがた)に[穢](けがれ)を移して[災い]を除けるといった習俗と、平安の頃からある、人形を用いた女児のおままごと[ひいな遊び](ヒナはサンスクリット語で「小さい」の意)が習合したものとされ、今も昔も女児の健康と幸福を願う大切な風習。
この[雛まつり]に飾る[雛人形]、豪華な七段飾りのものだと男雛に女雛、三人官女に五人囃子、それに随身、仕丁といった15体の人形たちに加え、六段目、七段目には[御輿入れ道具](嫁入り道具)が並ぶといった仕様が殆ど。
かつては、この[段飾り]を[嫁入り道具]として嫁ぐ娘に持たせたというのだから、女児の多い家はさぞ大変だったに違いない。地方によっては次女以降は[市松人形]を持たせるといった風習もあったというから、やっぱり[雛人形一式]を持たせての嫁入りは、嫁方の家計をかなり圧迫していたものと推察できよう。
ところで、その[豪華七段飾り]の[雛人形]の六段目、七段目に置かれるミニチュアの[御輿入れ道具]だが、大名家に伝わるとされる[御輿入れ道具]の実物(一部)が本学(国際文化理容美容専門学校 渋谷校/国分寺校)の『GALLERY 神泉』で披露されている旨は以前にもご紹介したが、先日、同ギャラリーを運営する[美容考古学研究所]の村田孝子 所長による[トークショー](展示物説明)が催され、この[御輿入れ道具]にまつわるハナシや、その他[簪](かんざし)、[櫛](くし)、歌川豊国の[美人画](浮世絵)など、展示物の微に入り細に穿(うが)った解説が行われ、参集した皆さんは、しばし江戸の[繊細な美意識]の世界にトリップしたようでありました。
残念ながら、この展示はすでに3月28日をもって終了しましたが、今後もさまざまなテーマのもと、新たな展示が企画されているようなので、乞うご期待なのであります。

SNS Share
MONTHRY ARCHIVE
東京の美容専門学校は国際文化理容美容専門学校。美容師・理容師の国家資格免許の取得に向けてヘアメイク・カット・ネイル・ブライダル・エステ・着付など、美容のすべてを学ぶ環境です。技術専門の教員が中心に授業や就職面をサポートします。また入学者を募集しています。総合型選抜(旧:AO入学)、学校推薦型選抜【指定校制】(旧:指定校推薦入学)、学校推薦型選抜【公募制】(旧:公募制推薦入学)、一般選抜(旧:一般入学)などのご相談は、オープンキャンパス・個別の見学会にてお待ちしております。
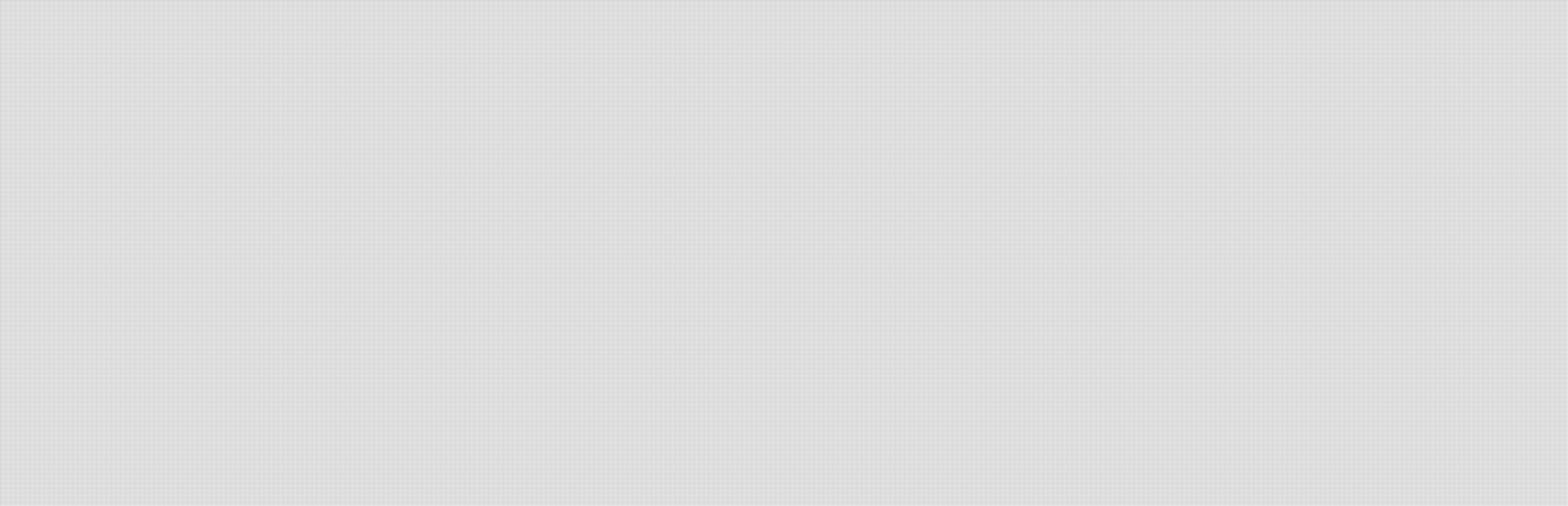









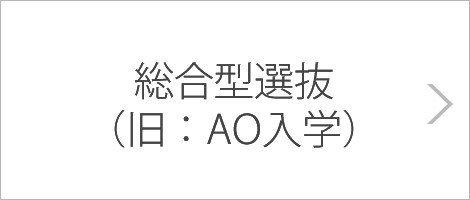


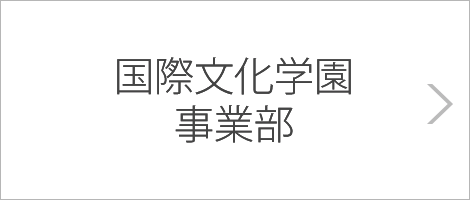
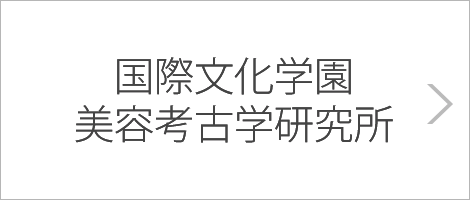

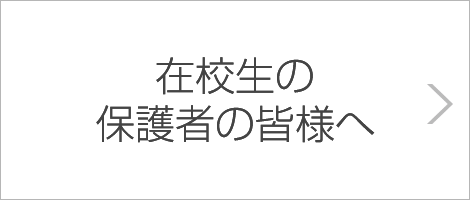


 ページ上部へ
ページ上部へ